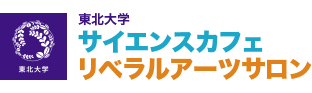2009年7月24日 第49回サイエンスカフェ
生き物とロボットのあいだ
~イグノーベル賞受賞研究から生まれた新しいロボット制御法とは?~
講師:石黒 章夫 東北大学大学院工学研究科 教授
プロフィール
 石黒先生は、生き物が示すしなやかで巧みな動きのからくりをロボット工学の観点から研究しています。IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS2004)最優秀論文賞、2008年イグノーベル賞(認知科学賞)など、国内外の多数の賞を受賞されています。
石黒先生は、生き物が示すしなやかで巧みな動きのからくりをロボット工学の観点から研究しています。IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems(IROS2004)最優秀論文賞、2008年イグノーベル賞(認知科学賞)など、国内外の多数の賞を受賞されています。
開催情報
開催日:2009年7月24日(金)18:00~19:45
会場 : せんだいメディアテーク
概要
地球から遙か遠くの天体へ宇宙探査機をピンポイントで到達させるなど、近年の最先端知能化技術の発展ぶりには目を見張るものがあります。しかしその一方で、単純な生き物ですら示すような、しなやかに環境に適応していく能力を工学的に実現するのはきわめて難しいのです。何とも皮肉なことではありませんか!では生き物はいったいどのような「からくり」を使ってこのような優れた振る舞いを実現しているのでしょうか?さらにはロボットがあたかも生き物のように「生き生きと」振る舞うためにはどのような工夫が必要なのでしょうか?
今回の講演では、真正粘菌という単細胞生物に着目することで浮かび上がってきた、生き物の巧みなからくりを使った新しいロボットの制御法を紹介したいと思います。現在のロボットと生き物の間に存在する大きな溝を埋めることにつながるかもしれません。
Q&A
分散処理の仕組みがよくわからない
分散処理とは,ひとつの高機能なシステムで処理させるのではなく,多数の比較的単純な要素を集めてその集団で処理させる方式です.ただし,私たちの興味がある分散処理は,単純に処理を分散したものではありません(例えば,ある仕事を100人で分担して行えば,一人あたりの仕事量は100分の一になるなど).個々の要素の相互作用を通して,個々の要素の単純性からは想像もできないような機能を全体のシステムから発現(創発)させることに興味があるのです.言い換えれば,1+1が2よりも大きくなるような効果(集団知)を要素集団に持たせることに興味があります.ただしこれをどのように行うのかはいまだによくわかっていません.私たちは真正粘菌という生き物からそのからくりを知りたいと考えています.
粘菌の多数の核は原形質に存在しているのですか。ゲル部分には存在していないのですか?それらの核同士の相互作用はあるのですか?それと粘菌の動きとの関係は?
核はゲルにもゾルの部分にも存在しています.また,核どうしは相互作用しております.その証拠は,核の分裂サイクルが同期していることです.粘菌を小さく切ったとき,核が一つも入らないように切ってしまうと,生きていくのは難しくなります.
自律分散制御はスタジアムの観客のウェーブですね。でもウェーブは自然な波に見えますが、ただ動いているだけで何の目的もないですよね。何らかのベクトルを与えないと動きにはならないのですが、どのようにして集権の分散のバランスをとるか難しいですね。ただ現在はその片方の研究を究めているという点、よくわかりました。
鋭いご指摘ですね.はい,中央集権的なシステムだけでは無理があるし,また分散だけのシステムでもできることは限られているでしょう.何事もそうなのですが,答えはどちらか一方ではなく,両者のバランスがとれているところが重要ですね.しかしながら,これまでのロボット制御は完全に中央集権的な制御手法に基づいており,分散制御に関してはほとんど行われていませんでした.これは,サイエンスカフェの時にもご説明させていただいたとおり,分散制御のからくりがまったくわかっていないからです.このため私たちは現在,徹底的に分散制御にこだわって研究を進めています.その後,(生物進化と同様に)集中と分散のバランスに関して考察を進めていきたいと考えております.
粘菌にたどりつくまでの過程を知りたい
これは研究経歴という意味でしょうか.だとすれば,私自身はずいぶんと遠回りをしてきました.昔はかなりの産業的な研究もしていましたし,完全に中央集権的なロボット制御もやっていました.しかしながら中央集権的な制御手法では,すぐに限界とぶち当たり,その後は試行錯誤の連続でした.生物のからくりを知りたいと深く思うようになったのはこの頃からですね.生き物のような「しぶとさ」や「したたかさ」はどのようなメカニズムから生み出されているのかを心から知りたいと思いました.徹底的に自律分散制御を考えていこうと決めた後も,かなりの紆余曲折がありました.その意味で,自律分散制御のからくりが凝縮されている真正粘菌に出会えたのは幸運だったと感じております.
今回説明していただいた研究について、先生がある程度納得するところまで研究が進んだとき、その研究を具体的に何に使いたいのか。
正直,応用はあまり考えておりません.私の興味は生き物とはなにか?,生き物のからくりとは?,生命現象はどのようにして生み出されているのか?,生き物が示す「しぶとさ」や「たくましさ」のからくりの理解にあります.その意味で私は,自分自身をロボットという道具を使う,新しいタイプの生物学や生物物理学の研究者だと思っています.
分散の仕組みを知りたい。
これは難しいです.いまだにわからないことばかりです.ほんのちょっとだけ見えてきたことがあるという感じでしょうか.
最終的には自分の意思で自然な動きを実現することは可能ですか?
これも難しい問題ですね.このためには,ロボットに動機付けや意思といった機能を実装しなければなりません.現在のところ,この部分には目をつぶっています.しかしながら,とてもチャレンジングな研究トピックであると感じています.
実際に自己修復できるようなロボットが作られるようになったら「生物」の概念が変わるんだろうなーと思います。何故日常的な動作にについてはあまり目が向けられなかったのでしょう(既にあるものだからあまり魅力的な研究対象に思えなったのでしょうか)。 面白かったので論文探して読んでみます。
はい,生き物のようにロボットが自己修復できたらおもしろいですね!これまでのように,「壊れないように機械を設計する」から「壊れても勝手に自己修復するように機械を設計する」へと,人工物の設計の仕方が劇的に変化するかもしれません.遙か遠くの天体に探査機を送り出したり,チェスの世界チャンピオンを打ち負かすようなプログラムができているのに,われわれが何気なく行っている動作を実現することが難しいのは確かに不思議ですね.それだけ生物のからくりは奥が深いということなのでしょうね.また,これまでの人工知能で実現されていた知能は,生物知能のごくごく一部だけ,ということなのでしょうね.
制御の難しさは粘菌ロボットよりヘビ型ロボットのほうが難しいのか。ヘビよりゴキブリのほうが動きの難しさとしては難しいのか?この目標を達成された後次は何を目指すのか?
これはとても重要な質問です.私たち自身もわかりません.まずは完全に自律分散的な制御が行われている粘菌を徹底的に調べ,自律分散制御でどこまでできるのかの限界を見届けないといけませんね.それがわかれば,生物は高等になるにつれて神経系を発達させていったことも,ロボットを通して理解できるのかもしれません.これは集中と分散のバランスにも絡むとても興味深い研究テーマでもあります.
ロボットを作った後、それをどの様に活かしていきたいのか。
これに関しては前の質問と同様に,私たちは応用にはあまり興味がありません.ただ,生き物のからくりを知りたいのです.そして,あたかも生きているとしか考えられないようなロボットも作ってみたいです.
真正粘菌類の生息できる場所はどんなところでしょうか?
森や薮の湿った「土や枯れ葉,朽ち木」の中です.
現在どの位研究が進んでいるのか(この後の進展は?)
まずは粘菌とヘビを徹底的に調べてみたいと思います.その後,昆虫などの多脚の生き物の動きを作り出すメカニズムの理解ですね.
粘菌の変形体は人間の手によって二つ以上に切り分けられますが自ら切り分けることはあるのですか?
あります.胞子をつくる時などはその一例です.変形体の時でも,たとえば迷路の場合,餌がたくさんあると最終的には二つの個体に分裂することもあります.
当日の様子