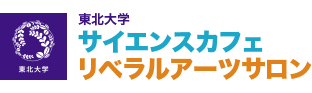2008年4月25日 第33回サイエンスカフェ
カーボンナノチューブの科学にようこそ ~円筒形物質の発見と使い方~
講師:齋藤 理一郎 東北大学大学院理学研究科 教授
プロフィール
 齋藤教授は、ナノチューブの理論的研究を発見当初から幅広く行っています。ナノチューブに関する論文で引用件数が100を超えるものが21本あり、そのうち1つは1000を超えています。1999年にIBM科学賞、2006年にHsun Lee Research Award を受賞しました。高校の出前授業や東京や名古屋のサイエンスカフェでも積極的に講演しています。趣味は畑仕事、卓球、テニス他。
齋藤教授は、ナノチューブの理論的研究を発見当初から幅広く行っています。ナノチューブに関する論文で引用件数が100を超えるものが21本あり、そのうち1つは1000を超えています。1999年にIBM科学賞、2006年にHsun Lee Research Award を受賞しました。高校の出前授業や東京や名古屋のサイエンスカフェでも積極的に講演しています。趣味は畑仕事、卓球、テニス他。
開催情報
開催日:2008年4月25日(金)18:00~19:45
会場 : せんだいメディアテーク
概要
p.s. 当日、はさみ、のり、定規、筆記用具、がありましたらお持ちくださいませ。
(こちらでも少し用意いたします。)
Q&A
ナノチューブの作り方の所にかいてあった数式の出所
講演者が導出しました。ナノチューブの教科書にもでています。講演者のWebページ以下にいろいろ情報があります。
カーボンナノチューブについて何を理論で考えるのですか。
ナノチューブという物の性質を考えます。何を考えたら役に立つかを考えます。実験でわからないことを説明します。
Ge、Siで同じことができるのか?
できません。炭素はその意味で非常に特殊であると思います。
単層フラーレンは柔らかく、多層フラーレンは固いとのことでしたが、どれくらい固いか教えていただきたいです。(同素体の黒鉛は柔らかく、ダイヤモンドは固いとなっておりますが、これらと比較した時の硬さを教えていただきたいです)
専門的な質問ですので、専門的にお答えします。硬さは体積弾性率という数値で評価します。単層ナノチューブがやわらかく、多層ナノチューブが固いと申しました(フラーレンではありません。)この場合には、ナノチューブの折り曲げやすさに対する固さです。ダイヤモンドが固いというのは、体積弾性率の本来の固さです。グラファイトがやわらかいのは、層状構造をとっているのでそれぞれの原子層が曲がりやすいという意味でやわらかいです。いずれも数値で比較できますが、意味がそれぞれ違います。
カーボンナノチューブの熱伝導率が高いのはなぜだろうか?チューブの中に原子を入れたら原子は動き続けるのだろうか?
熱伝導率が高い理由は、(1)結合が非常に強いこと、(2)原子が軽いこと、によります。熱の伝導は、原子の振動が関係しています。振動は、地震のように波で伝わりますが、熱は少し別の仕組みで伝わります。大学3年生ぐらいになると勉強します。ナノチューブの中にいる原子は、自由に動くことができます。いっぱいに詰まっていたり、水が氷になるように固体になると動きにくくなります。
熱伝導性は金属の10倍。なら電気伝導性はどれぐらいになるのでしょうか。
電気伝導は、銅よりも伝導性が良いですが、10倍はいかないと思います。電気伝導は、(1)電子の数、(2)電子1個の動きやすさ(移動度といいます)の積になります。ナノチューブは、動きやすさは抜群なんですが電子の数が銅などに比べてあまりありません。それでも、匹敵する電気伝導度が出るのはすごいですね。
ナノチューブの使い方で光というお話がありましたが、最近のニュースで白熱灯の使用禁止の話を聞き、これに代わる物として(かなり効率もいいようなので)使えないものなのでしょうか?又、使えるとして、大きさや光度、消費電力はどうでしょう?
使えると思います。講演のときにお見せした蛍光表示管を電球代わりに使うことで蛍光灯以上の効率を出すことができるかもしれません。輝度、消費電力は白熱電球を超えるのは容易で実現できています。ですが実用となると、発光ダイオード以上の効率をださないと、業界は動かないと思います。技術の進歩を期待したいですね。
放射性物質などをナノチューブに入れると崩壊のスピードはかわるのですか。
非常に難しい質問で、答えるのにだいぶ考えました。放射性物質の崩壊は、原子核の中の反応ですので、その意味では原子の外側をナノチューブで包んでもかわらないと思います。ですが、ナノチューブの中で高速で放射性物質を動かすことができれば、寿命を延ばすことができるかもしれません。相対論的な効果です。講演では、反物質(反陽子と陽電子、反中性子からなる反原子からできる物質)からとよばれる物質をいれると安定に存在できるかもしれないとお話しました。専門の方でしたら、ぜひ議論させてくださいませ。
カーボンナノチューブをC原子1つ1つで掴んで組み立てることはできるのですか?原子レベルの機械ができたら倫理上危ないですよね。
原理的につかんで組み立てることは可能だと思いますが、実際に行った例はありません。まだそこまでの技術はありません。原子レベルの機械ができても、倫理上の問題はないと思います。科学の進歩は、常に悪用されることに対して注意する必要があります。
ナノチューブの大きさを自在につくることができるのですか。また、具体的にどういう方法で?(ナノチューブ内の電子の状態を知りたかった)
できます。ナノチューブの直径は、反応温度を調整することでコントロールできます。またナノチューブ内の電子の状態は、サイエンスカフェでお話しするのはちょっと難しいですね。大学の授業を勉強したあとで大学院の授業ぐらいで紹介できると思います。大学院の集中講義などでお話することはございます。
mとnの値を変えることで多様なナノチューブができるようですが、これらは実用上でどのように使い分けているのですか。
金属と半導体のチューブをつかいわけることができます。金属と半導体はm とn の値に依存してどちらかの性質になります。
どこまで大きいサッカーボールができるのか?現実にはどこまで太いナノチューブができるのか?ナノチューブの直径、nとmの選び方について…
C200ぐらいまでは、合成できています。単層ナノチューブの直径で、大きいものは3nmぐらいまでです。多層なのチューブは、いくらでも太くできます。1000nmぐらいの同心の炭素繊維が作られています。質問が途中で切れていますが、直径やnやmを個別に選ぶ技術はまだできていません。これを実現することは、日本の研究グループを始め世界の研究者が挑戦しています。何かいいアイデアがあったら教えてくださいませ。
ナノチューブの大きさ、形により、なぜ半導体型、金属形ができるのか。サイズ・形を特定して作ることができますか。実験、条件の見つけ方があるのでしょうか。
この質問の答えは、たとえば私の教科書には書いてあるのですが、金属と半導体ができることを説明するのには、量子力学という物理の学問を勉強して、さらに固体物理学を勉強する必要があります。その言葉を使わないで説明できれば、私もブルーバックスが書けるのではないかと思っています。サイズ、形を特定して作ることは、あまり実現できていません。混合物ができて、そのなかから色々な大きさのものを、ふるいにかけて分けることはフラーレンなどではできています。
工業製品、原料として供給するにはサイズや純度をコントロールする必要があると思うのですが、そのあたりはどうコントロールしているのですか?(以前は不純物が多く混じっていたり、サイズがコントロールできない(むずかしい)と聞いたことがあるので不思議です)
反応温度などの条件を変えることで、コントロールができつつあります。様々な条件を系統的に変えて、結果をみていく手法として、コンビナトリ法というのがあるのですが、ナノチューブでも応用して加速度的に研究が進展しています。
カーボンナノチューブでドーナツ型のものや板状のものなどチューブ以外には出来るのでしょうか。又、毒性のある物質を包むことで毒の影響をなくせるとあったが移植の拒絶反応の軽減に使えるでしょうか
ドーナッツ形のものを見たという論文はあります。ですが、完全にドーナッツ形になっていなくて、ナノチューブをドーナッツ形に丸めただけのものです。端をつなげることができれば完成します。またフラーレンの真ん中に穴を貫通させて結合させればドーナッツ形にできますが、方法はわかっていません。板状のものは、ナノリボンと呼ばれて作られています。拒絶反応は免疫の仕組みであると思いますが、私の知る限りでは、免疫反応を軽減することに応用された例はないと思います。どうやったら免疫反応が軽減できるか?をナノチューブの研究者が知らないと解けない問題ですね。
ナノチューブのこれからの使い道。
さらに挑戦を続けていけば道は開けると思います。つかいみちは、新しい発想と挑戦が必要だと思います
これからフラーレンやカーボンナノチューブを使ってどんな物を作っていくのですか?
実は、ここがもっとも重要なところです。講演でお話した応用は、ごく一部でしかありません。サイエンスカフェで皆さんのアイデアを是非よせて欲しいと思っています。
当日の様子